|
3/11 |
脳の可塑性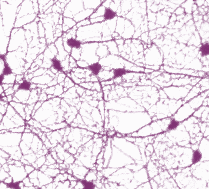 脳は、数百億という驚異的な数の神経細胞が集まってできています。そしてそれらが適当な時に適当な反応を起こすことで、脳の機能が遂行されます。個々の神経細胞には入力と出力があり、これが右図で見るように相互に非常に密接かつ複雑に関係しあって、綿密な神経回路を形成しています。そして、ちょうどコンピューターが電気回路を使って情報の処理・蓄積を行っているように、脳はこの神経回路を使って情報を管理しています。回路のつながり具合によって、どう情報が処理されるかが決定されるのです。したがってどの様に神経が回路を形成しているか、ということが脳にとって非常に重要な問題となってくるわけです。逆に、人が物事を記憶するときには、まさにこの神経回路の形態が変化することによって情報を蓄積するといえます。つまり脳の可塑性は、新しい神経回路の形成によって生じるのです。この意味で、「記憶する時に脳のなにかが変化する」の、なにかとは神経回路だ、といえます。 脳は、数百億という驚異的な数の神経細胞が集まってできています。そしてそれらが適当な時に適当な反応を起こすことで、脳の機能が遂行されます。個々の神経細胞には入力と出力があり、これが右図で見るように相互に非常に密接かつ複雑に関係しあって、綿密な神経回路を形成しています。そして、ちょうどコンピューターが電気回路を使って情報の処理・蓄積を行っているように、脳はこの神経回路を使って情報を管理しています。回路のつながり具合によって、どう情報が処理されるかが決定されるのです。したがってどの様に神経が回路を形成しているか、ということが脳にとって非常に重要な問題となってくるわけです。逆に、人が物事を記憶するときには、まさにこの神経回路の形態が変化することによって情報を蓄積するといえます。つまり脳の可塑性は、新しい神経回路の形成によって生じるのです。この意味で、「記憶する時に脳のなにかが変化する」の、なにかとは神経回路だ、といえます。では、新しい神経回路を形成するために脳はいかなるメカニズムを用意しているのでしょうか。下図に、新しい神経回路を形成することができる機構を思いつくままに3つ挙げてみました。 1つ目の仮説は、神経細胞が増殖することで新しい回路が生成するものです。Aの神経細胞が出力側、Bが入力側で、この2つの細胞はシナプスによってA→Bという結合をしています。ここに新しい神経細胞Cが増殖によって現れ、A→C→Bという新しい回路が形成されます。 2つ目の機構は、新しくシナプスが発生するものです。ここにA、B、Cの3つの神経細胞があったとします。始めはA→Bの回路しかなかったものが、のちにAがCにも出力するようになり新しくA→Cという回路が生成します。これは「発芽」と呼ばれています。 3つ目の機構は、シナプスの伝達効率が上昇するものです。これは見かけ上は神経細胞の数も、シナプスの数も変化しないのですが、神経細胞と神経細胞の間で信号のやりとりがし易くなるというもので、電気回路でいうのなら抵抗が小さくなって電気が流れやすくなる現象に例えられるでしょう。いつもは抵抗の大きな、つまり伝達効率のよくないシナプスで殆ど利用されていなかったものが、抵抗が小さくなり情報がスムーズに伝達できるようになれば、これは新しい回路が形成されたと考えられます。これを「シナプス可塑性」と呼んでいます。 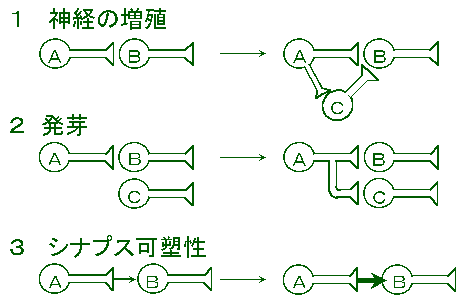 以上のような3つの仮説を挙げてみましたが、脳は新しい回路を形成するために一体どの機構を用いているのでしょうか。まず1つ目の機構はありえないでしょう。なぜなら神経細胞は増殖しないからです。実際、脳の神経細胞の数は生まれたときが一番多く、年齢を経るに従って減っていきます。従って、神経細胞が増えることによって新しい回路が形成されることはありえません。残りの仮説は、シナプスの発芽とシナプスの可塑性です。このどちらの機構を脳が使用しているかは、日頃体験することを考えてみれば自ずと明かです。例えば、電話をかけるとき、私達は電話帳を見て電話番号を暗唱しダイヤルを回すことができます。この時、電話番号を覚えるのに要する時間は秒単位です。一方、シナプスの発芽には、通常数時間から数日といった長時間を必要とします。従って、発芽は記憶のメカニズムとしては不合格です。ただし大脳皮質の一部には、発芽という現象が確認されていますので、短期的な記憶ではなくもっと長期に渡る記憶の保持に関係しているのかもしれません。残る仮説はシナプス可塑性ですが、これはシナプスの抵抗を変化させるだけのもので、これならば瞬時に行なえそうです。実際に現在では、シナプス可塑性は記憶・学習の基礎をなすメカニズムの1つであるというコンセンサスは十分に得られています。しかし、そもそも脳においてシナプス可塑性は存在するのでしょうか。それとも机上の空論に過ぎないのでしょうか。ここではまず、記憶に関与するとされるシナプス可塑性の性質について考えてみましょう。 |